2016年05月26日
神保町にて
もじゃもじゃです!
先日神保町の「軍学堂」さんにて「アルビン・トフラーの戦争と平和」を購入しました。
軍学堂さんは旧軍関係の書籍や資料が多く、WEB店舗もお持ちの古書店。
初めてお伺いしたので、何か1点でも購入したいと思い、隅から隅まで棚をチェックしたところ、現在は絶版になっている「アルビン・トフラーの戦争と平和」を発見。
本書は以前本ブログでご紹介した「現代の軍事戦略入門」
で度々触れられていたので、気になっていました。
内容はトフラーの「第三の波」で取り上げられなかった、「戦争」が知識社会化の中でどのように変容していくのかについての考察のようで、まだ前書きと後書きしか読んでいませんが、RMA関連書としても面白そう。
内容については、読後に本ブログにて紹介致しますが前書き・プロローグに印象的な部分があったので、ちょっとフライング。
「しばしば非難されることだが、高級将校たちは前回と同じ戦争を、今一度戦おうと考え、その準備に時間を費やしている。(中略)
平和のために言論活動をしていると思っている知識人、政治家、反戦運動家たちにも時代遅れの高級将校に対するのと同じ批判が向けられて然るべきだということだった」
先日新宿で若者主体の反戦デモを目撃したときに感じた違和感を、上記の言葉が代弁してくれているように感じました。

先日神保町の「軍学堂」さんにて「アルビン・トフラーの戦争と平和」を購入しました。
軍学堂さんは旧軍関係の書籍や資料が多く、WEB店舗もお持ちの古書店。
初めてお伺いしたので、何か1点でも購入したいと思い、隅から隅まで棚をチェックしたところ、現在は絶版になっている「アルビン・トフラーの戦争と平和」を発見。

本書は以前本ブログでご紹介した「現代の軍事戦略入門」
で度々触れられていたので、気になっていました。
内容はトフラーの「第三の波」で取り上げられなかった、「戦争」が知識社会化の中でどのように変容していくのかについての考察のようで、まだ前書きと後書きしか読んでいませんが、RMA関連書としても面白そう。
内容については、読後に本ブログにて紹介致しますが前書き・プロローグに印象的な部分があったので、ちょっとフライング。
「しばしば非難されることだが、高級将校たちは前回と同じ戦争を、今一度戦おうと考え、その準備に時間を費やしている。(中略)
平和のために言論活動をしていると思っている知識人、政治家、反戦運動家たちにも時代遅れの高級将校に対するのと同じ批判が向けられて然るべきだということだった」
先日新宿で若者主体の反戦デモを目撃したときに感じた違和感を、上記の言葉が代弁してくれているように感じました。

2016年04月26日
「中国4.0 暴発する中華帝国」 その2
さて、エドワード・ルトワック著 奥山真司訳 文春新書刊の「中国4.0 暴発する中華帝国」。
先日は「その1」として、2000年以降の中国の対外政策と、なぜ暴発したかの理由までをまとめた。
本日はルトワック氏が提案する日本がとるべき対応策(本書5章)についてご紹介したい。
もし、尖閣諸島が中国に占領されたとしたら、日本はどのような対応をとるべきだろうか?
封じ込め政策
中国は巨大な人口と経済力・軍事力を持つ大国である。
しかし、現状はアフリカの独裁的小国なみに不安定である。
不安定で先行きの予測ができない大国への対応としては、極めて受動的な「封じ込め」政策が有効である。
「封じ込め」とは、ひたすら相手に「反応」することに主眼を置く政策である。
もし尖閣を占領されたら⇒即時に反応
もし中国が尖閣を占領したとしたら、日本は「即時」に反応しなければならない。
(南シナ海のスプラトリー諸島で他国の島をとって基地を建設してしまうような)中国に対抗するため、島を占拠されたら、誰にも相談することなく奪還するメカニズムが不可欠である。
アメリカや国連に頼ったり、国会で議論などしてモタモタしていたら、ロシアにクリミア半島を奪われたウクライナの二の舞になる。
アフリカのフランス領マリをアルカイダに占領された際、フランスのオランド大統領は、電話1本で軍の進駐を命じた。
日本にもこのようなメカニズムが必要である。
もし尖閣を占領されたら⇒多元的な能力行使
多元的とは、日本の関係組織それぞれが、自律的に行動するということ。
各組織とは、海自・海保・陸自・空自そして、外務省も含まれる。
武力的実行力のある各組織は島の奪還作戦を、外務省はアメリカ、東南アジア、EU等に働きかけ、中国を尖閣から追い出す為の策を実施する。
たとえば、外務省はEUに働きかけ、中国の船の入管手続きを遅延させ、経済的打撃を与えるなどの手段がある。
もし尖閣を占領されたら⇒アメリカの支援
日本は即時的・多元的に行動しつつも、アメリカの支援を必要とする。
しかし、アメリカの公式な立場は「領土紛争では中立的立場を守る」というもの。
つまり、どのような支援をするかはアメリカ大統領の決断いかんであり、その決断はその時のアメリカの国内事情、米国民のムードによる。
アメリカは「日本の根幹としての統治機構システム」を守る意思と装備は持っている。
が、人が住まないような小さな島まで守るような想定はない。
日本が小さな島一つ自分で守れないのであれば、米側に過大な負担を与え、日米関係に悪影響を与える。
つまり、日本は島の奪還は自らの判断で自らの力で行わなければならない。
以上、今回は、日本の対応に的を絞って主に本書の第5章を中心にまとめた。
本書には他にも、習近平に関する考察、韓国が日本を恨む理由、国家が戦略を誤る理由、「大国は小国に勝てない」「海洋パワーとシーパワー」「戦略文化」など、本ブログでは触れてはいないが、刺激的な内容に満ちている。
また、「自滅する中国」と合わせて読むことで、戦略的に中国を理解することができるだろう。
6章では、本書のインタビューと訳を担当された地政学者・奥山氏が本書のエッセンスをまとめている。
本書の理解だけでなく、「戦略論」を含めたルトワック氏の理論の理解の一助になるので、お勧めである。
最後にタイトルにもなっている「中国4.0」なるルトワック氏が提案する中国の対外政策とはどのようなものか?
それは、皆さんが書店で本書を手にとって、ご自身で確かめられたい。

先日は「その1」として、2000年以降の中国の対外政策と、なぜ暴発したかの理由までをまとめた。
本日はルトワック氏が提案する日本がとるべき対応策(本書5章)についてご紹介したい。
もし、尖閣諸島が中国に占領されたとしたら、日本はどのような対応をとるべきだろうか?
封じ込め政策
中国は巨大な人口と経済力・軍事力を持つ大国である。
しかし、現状はアフリカの独裁的小国なみに不安定である。
不安定で先行きの予測ができない大国への対応としては、極めて受動的な「封じ込め」政策が有効である。
「封じ込め」とは、ひたすら相手に「反応」することに主眼を置く政策である。
もし尖閣を占領されたら⇒即時に反応
もし中国が尖閣を占領したとしたら、日本は「即時」に反応しなければならない。
(南シナ海のスプラトリー諸島で他国の島をとって基地を建設してしまうような)中国に対抗するため、島を占拠されたら、誰にも相談することなく奪還するメカニズムが不可欠である。
アメリカや国連に頼ったり、国会で議論などしてモタモタしていたら、ロシアにクリミア半島を奪われたウクライナの二の舞になる。
アフリカのフランス領マリをアルカイダに占領された際、フランスのオランド大統領は、電話1本で軍の進駐を命じた。
日本にもこのようなメカニズムが必要である。
もし尖閣を占領されたら⇒多元的な能力行使
多元的とは、日本の関係組織それぞれが、自律的に行動するということ。
各組織とは、海自・海保・陸自・空自そして、外務省も含まれる。
武力的実行力のある各組織は島の奪還作戦を、外務省はアメリカ、東南アジア、EU等に働きかけ、中国を尖閣から追い出す為の策を実施する。
たとえば、外務省はEUに働きかけ、中国の船の入管手続きを遅延させ、経済的打撃を与えるなどの手段がある。
もし尖閣を占領されたら⇒アメリカの支援
日本は即時的・多元的に行動しつつも、アメリカの支援を必要とする。
しかし、アメリカの公式な立場は「領土紛争では中立的立場を守る」というもの。
つまり、どのような支援をするかはアメリカ大統領の決断いかんであり、その決断はその時のアメリカの国内事情、米国民のムードによる。
アメリカは「日本の根幹としての統治機構システム」を守る意思と装備は持っている。
が、人が住まないような小さな島まで守るような想定はない。
日本が小さな島一つ自分で守れないのであれば、米側に過大な負担を与え、日米関係に悪影響を与える。
つまり、日本は島の奪還は自らの判断で自らの力で行わなければならない。
以上、今回は、日本の対応に的を絞って主に本書の第5章を中心にまとめた。
本書には他にも、習近平に関する考察、韓国が日本を恨む理由、国家が戦略を誤る理由、「大国は小国に勝てない」「海洋パワーとシーパワー」「戦略文化」など、本ブログでは触れてはいないが、刺激的な内容に満ちている。
また、「自滅する中国」と合わせて読むことで、戦略的に中国を理解することができるだろう。
6章では、本書のインタビューと訳を担当された地政学者・奥山氏が本書のエッセンスをまとめている。
本書の理解だけでなく、「戦略論」を含めたルトワック氏の理論の理解の一助になるので、お勧めである。
最後にタイトルにもなっている「中国4.0」なるルトワック氏が提案する中国の対外政策とはどのようなものか?
それは、皆さんが書店で本書を手にとって、ご自身で確かめられたい。

2016年04月14日
「中国4.0 暴発する中華帝国」 その1
もじゃもじゃです!
さて、先日の「戦略論」に引き続き「最強の」戦略家ルトワック氏の最新作を紹介。
本書は日本の地政学者奥山真司氏がルトワック氏に行ったインタビューを元に構成されており、非常に読みやすい。
新書ということもあり、売れているようで、3月20日出版後、現在書店に並んでいるのは既に3刷である。
内容は2000年代からの中国の対外政策を、中国(チャイナ)1.0=平和的台頭、、中国2.0=対外強硬路線、中国3.0=選択的攻撃に
分類し、中国の今後の方向性(中国4.0)と日本の対応策について書かれている。
「自滅する中国」の続編にあたるが、それだけにとどまらずルトワックの「戦略論」を理解する入門書的な役割も果たしている。
また、最近の情勢も取り込まれており、インタビューが元ということで日本向けを意識した最新の中国論でもある。
まずは前提となる、2000年以降の中国の対外政策を簡潔にまとめてみると、
中国(チャイナ)1.0=平和的台頭→2000年以降リーマンショックまで
・国際秩序に従い、領海、経済ルール、金融取引等各種国際ルールに従いながら、発展。
・経済の発展と相まって、国際的にも受け入れられていた。
中国2.0=対外強硬路線→リーマンショック後
・リーマンショックをきっかけにアメリカの衰退が始まるや、対外強行路線に転じる。
・日本との尖閣を巡るトラブルをはじめ、インド、フィリピン、ベトナムとの領土問題が蒸し返される。
・結果として、反中同盟が徐々に結成されはじめる。
中国3.0=選択的攻撃→現在
・抵抗のないところには攻撃に出て、抵抗のあるところには攻撃しない。
・日本やインド等にはあからさまな行動には出ないが、フィリピンやミャンマーなど抵抗のない親中国で経済的・領土的問題を起こし、親中国をも遠ざける結果となっている。
なぜ、中国がリーマンショック後対外強硬路線に走り、世界中で反感を買い、アメリカをして決定的に中国を敵対視させ、日本の警戒感を増幅させるような国際情勢を作り出してしまったかについて
著者は3つの中国の錯誤をあげている。
①国力と経済力のずれ・・経済力が実際に国力(国際社会でのパワー)に反映されるまで、50年~100年のタイムラグがある。
②線的予測・・リーマンショック時のアメリカの衰退・中国の勃興傾向がそのまま続くという思い込み。
③大国は二国間関係をもてない・・中国は問題を当事国(主にアジアの小国)との2国間で解決したがる。
しかし、中国を脅威と感じる他の大国が介入して来るため、実質的に2国間での関係は保てない。
19世紀半ばから日本等列強に支配されたうらみ「百年国恥」を、経済的・軍事的に力をつけ、アメリカが相対的に衰退の兆しを見せた時から、中国は3つの錯誤によって戦略を誤った。
では、著者が提案する「中国4.0」とはどのような戦略なのだろうか?
また、日本が取るべき対応とはどのようなものだろうか?
次回、その2に続きます!

さて、先日の「戦略論」に引き続き「最強の」戦略家ルトワック氏の最新作を紹介。
本書は日本の地政学者奥山真司氏がルトワック氏に行ったインタビューを元に構成されており、非常に読みやすい。
新書ということもあり、売れているようで、3月20日出版後、現在書店に並んでいるのは既に3刷である。
内容は2000年代からの中国の対外政策を、中国(チャイナ)1.0=平和的台頭、、中国2.0=対外強硬路線、中国3.0=選択的攻撃に
分類し、中国の今後の方向性(中国4.0)と日本の対応策について書かれている。
「自滅する中国」の続編にあたるが、それだけにとどまらずルトワックの「戦略論」を理解する入門書的な役割も果たしている。
また、最近の情勢も取り込まれており、インタビューが元ということで日本向けを意識した最新の中国論でもある。
まずは前提となる、2000年以降の中国の対外政策を簡潔にまとめてみると、
中国(チャイナ)1.0=平和的台頭→2000年以降リーマンショックまで
・国際秩序に従い、領海、経済ルール、金融取引等各種国際ルールに従いながら、発展。
・経済の発展と相まって、国際的にも受け入れられていた。
中国2.0=対外強硬路線→リーマンショック後
・リーマンショックをきっかけにアメリカの衰退が始まるや、対外強行路線に転じる。
・日本との尖閣を巡るトラブルをはじめ、インド、フィリピン、ベトナムとの領土問題が蒸し返される。
・結果として、反中同盟が徐々に結成されはじめる。
中国3.0=選択的攻撃→現在
・抵抗のないところには攻撃に出て、抵抗のあるところには攻撃しない。
・日本やインド等にはあからさまな行動には出ないが、フィリピンやミャンマーなど抵抗のない親中国で経済的・領土的問題を起こし、親中国をも遠ざける結果となっている。
なぜ、中国がリーマンショック後対外強硬路線に走り、世界中で反感を買い、アメリカをして決定的に中国を敵対視させ、日本の警戒感を増幅させるような国際情勢を作り出してしまったかについて
著者は3つの中国の錯誤をあげている。
①国力と経済力のずれ・・経済力が実際に国力(国際社会でのパワー)に反映されるまで、50年~100年のタイムラグがある。
②線的予測・・リーマンショック時のアメリカの衰退・中国の勃興傾向がそのまま続くという思い込み。
③大国は二国間関係をもてない・・中国は問題を当事国(主にアジアの小国)との2国間で解決したがる。
しかし、中国を脅威と感じる他の大国が介入して来るため、実質的に2国間での関係は保てない。
19世紀半ばから日本等列強に支配されたうらみ「百年国恥」を、経済的・軍事的に力をつけ、アメリカが相対的に衰退の兆しを見せた時から、中国は3つの錯誤によって戦略を誤った。
では、著者が提案する「中国4.0」とはどのような戦略なのだろうか?
また、日本が取るべき対応とはどのようなものだろうか?
次回、その2に続きます!

2016年04月06日
汝 平和を欲するなら 戦いに備えよ
もじゃもじゃです!
以前紹介した自滅する中国の著者で実務派戦略研究家エドワード・ルトワック氏の代表的著書「戦略論 戦争と平和の論理」を、今回ご紹介。
・本書は8カ国以上で翻訳され、戦略教育の現場で活用されている現代の古典的名著。
著者のルトワック氏はいわゆる学者タイプではなく、各国政府や民間企業のコンサルタントとして現場で活躍している現役の実務派戦略家。(特殊部隊へのアドバイスも行っているとか)
本作が代表作と言われている。
・今回のタイトル「汝 平和を欲するなら 戦いに備えよ」は本書の主要テーマである逆説的論理を簡潔に顕すローマ時代の格言である。ラテン語では「Si vis pacem, para bellum」。
ガンファンにはおなじみのカートリッジ9mmパラベラムの「パラベラム」は、この警句から取られたとか。
さて、「戦略論」の大きな特徴として2点。
①戦略を垂直面と水平面でモデル化。
②戦略の世界は逆説的論理に満ちている。
①戦略を垂直面と水平面でモデル化
・戦略の概念は、垂直面と水平面に分かれる。
・垂直面は下から「技術」⇒「戦術」⇒「作戦」⇒「戦域戦略」⇒「大戦略」によって構成されている。
水平面は、敵と味方の間で行われる活動の作用と反作用(攻撃と反撃etc)が、垂直面の各レベルで行われる。
・最も重要なのは一番上の「大戦略」。垂直面において、下の「技術」から優れていても、「大戦略」誤っていると戦争には勝てない。
優秀な兵器と陸軍で戦闘に勝ち続けヨーロッパをほぼ制圧しても、最終的には同盟国の選択を誤った結果敗北したナチスドイツが一例。
②戦略の世界には逆説的論理に満ちている
・逆説的とは、物事を原因、過程、結果と直線的にシンプルに考える一般的な思考モデルとは異なり、対立する相手との相互作用によって物事の形勢が反対方向に転じるという意味。
戦争におけるひとつひとつの行動はシンプルなものであるが、戦争では敵味方がお互いの手段に対して対抗したり妨害しようとしたりする結果、一般的な「原因→過程→結果」どおりには進まない。
・例えば、人や物資を輸送する際、平時であれば、スピードを出せて大量の人員・物資を快適に輸送できる広くて整備された道を選ぶだろう。
しかし、戦時には広くて整備された道は、敵にとっても有利であり、待ち伏せや妨害・奇襲等に合いやすい為、平時には非合理的な狭くて険しい道を、しかも夜の雨の日に選んだりする。

本書では、逆説的論理を豊富な事例を交えて解説がなされている。が、一般の人には難解な本である。
文章が難解な上に、ある程度の軍事史の知識が必要だからである。
また、ビジネス戦略書では、まとめ的なページや章があるものだが、本書にはほぼない。
しかし、難解な「戦略論」も同じルトワック氏の「自滅する中国」を副読本として活用することで、私を含めた一般の人にも戦略に対する理解が深まる。
現在、日本をはじめアメリカ、東南アジア諸国の大きな脅威となりつつある中国の動向をルトワック氏の著作を通じて戦略面から理解することで、戦略が生きた知恵となってくる。
興味を持たれた方は、まずは自滅する中国をおすすめする。ちょっと分厚い本は・・・という方にはルトワック氏の最新刊「中国4.0 暴発する中華帝国」から入っても良いかもしれません。
※文中、一部「自滅する中国」解説から引用させて頂きました。
以前紹介した自滅する中国の著者で実務派戦略研究家エドワード・ルトワック氏の代表的著書「戦略論 戦争と平和の論理」を、今回ご紹介。
・本書は8カ国以上で翻訳され、戦略教育の現場で活用されている現代の古典的名著。
著者のルトワック氏はいわゆる学者タイプではなく、各国政府や民間企業のコンサルタントとして現場で活躍している現役の実務派戦略家。(特殊部隊へのアドバイスも行っているとか)
本作が代表作と言われている。
・今回のタイトル「汝 平和を欲するなら 戦いに備えよ」は本書の主要テーマである逆説的論理を簡潔に顕すローマ時代の格言である。ラテン語では「Si vis pacem, para bellum」。
ガンファンにはおなじみのカートリッジ9mmパラベラムの「パラベラム」は、この警句から取られたとか。
さて、「戦略論」の大きな特徴として2点。
①戦略を垂直面と水平面でモデル化。
②戦略の世界は逆説的論理に満ちている。
①戦略を垂直面と水平面でモデル化
・戦略の概念は、垂直面と水平面に分かれる。
・垂直面は下から「技術」⇒「戦術」⇒「作戦」⇒「戦域戦略」⇒「大戦略」によって構成されている。
水平面は、敵と味方の間で行われる活動の作用と反作用(攻撃と反撃etc)が、垂直面の各レベルで行われる。
・最も重要なのは一番上の「大戦略」。垂直面において、下の「技術」から優れていても、「大戦略」誤っていると戦争には勝てない。
優秀な兵器と陸軍で戦闘に勝ち続けヨーロッパをほぼ制圧しても、最終的には同盟国の選択を誤った結果敗北したナチスドイツが一例。
②戦略の世界には逆説的論理に満ちている
・逆説的とは、物事を原因、過程、結果と直線的にシンプルに考える一般的な思考モデルとは異なり、対立する相手との相互作用によって物事の形勢が反対方向に転じるという意味。
戦争におけるひとつひとつの行動はシンプルなものであるが、戦争では敵味方がお互いの手段に対して対抗したり妨害しようとしたりする結果、一般的な「原因→過程→結果」どおりには進まない。
・例えば、人や物資を輸送する際、平時であれば、スピードを出せて大量の人員・物資を快適に輸送できる広くて整備された道を選ぶだろう。
しかし、戦時には広くて整備された道は、敵にとっても有利であり、待ち伏せや妨害・奇襲等に合いやすい為、平時には非合理的な狭くて険しい道を、しかも夜の雨の日に選んだりする。

本書では、逆説的論理を豊富な事例を交えて解説がなされている。が、一般の人には難解な本である。
文章が難解な上に、ある程度の軍事史の知識が必要だからである。
また、ビジネス戦略書では、まとめ的なページや章があるものだが、本書にはほぼない。
しかし、難解な「戦略論」も同じルトワック氏の「自滅する中国」を副読本として活用することで、私を含めた一般の人にも戦略に対する理解が深まる。
現在、日本をはじめアメリカ、東南アジア諸国の大きな脅威となりつつある中国の動向をルトワック氏の著作を通じて戦略面から理解することで、戦略が生きた知恵となってくる。
興味を持たれた方は、まずは自滅する中国をおすすめする。ちょっと分厚い本は・・・という方にはルトワック氏の最新刊「中国4.0 暴発する中華帝国」から入っても良いかもしれません。
※文中、一部「自滅する中国」解説から引用させて頂きました。
2015年12月09日
「自滅する中国 なぜ世界帝国になれないのか」
「自滅する中国 なぜ世界帝国になれないのか」エドワード・ルトワック著 奥山真司監訳
もじゃもじゃです!
今回は反中派の人が泣いて喜びそうなタイトルの本をご紹介。
ただ、この本はバリバリの現役戦略家が書いた戦略本であり、巷にあふれる反中意識を煽るような安易な本ではありません。
著者ルトワック氏は、ワシントンのシンクタンクCSISの上級アドバイザー。
ホワイトハウスの国家安全保障会議のメンバーも務めたこともある文武両道の実務派。
氏自身が中東戦争への従軍経験があり、今でもアドバイザーとして危険な現場へ出向く事もある。
氏の名声は著書「戦略論」によるところが大きく、「戦略論」は世界各国の戦略教育現場で必読書となっている。
さて、本書の内容を簡単にまとめると、
①増大する中国のパワー(経済力・軍事力・国際的発言力)に対する近隣諸国含めた他国の警戒姿勢が強まる。
・中国の年率8%のGDP成長率、ほぼ同じ程度の軍事費の増加を背景に中国は国際的存在感を増してきた。
・2009年までは中国は「平和的に台頭」していたが、2010年の経済危機を境に、他国に対して傲慢な姿勢をあからさまにし始めた。
日本、フィリピン、ベトナムとの施設や領土を巡る紛争。最近では南シナ海の埋め立て問題等。
・この動きに対して米軍の中東から太平洋へのシフト、日本を含む近隣諸国の防衛的協力体制の構築。(例えば、日本がベトナムに資金援助を行いベトナムがロシア製潜水艦を購入、ロシア製潜水艦をすでに使用しているインドが潜水艦経験の浅いベトナムに対して自国の基地を使用した教育を提供)
が行われている。
・オーストラリアは、(経済的に中国への依存度が高いにも関わらず)日本を含め積極的にアジア各国との(対中)連携を強めている。
②その状況を正確に把握できない中国の「大国自閉症」
・中国の傲慢な行動・発言に対して、既に各国から非難の声や態度は明確になっているが、中国はその方針を改めない。
・また国際社会での経験も浅く、外国への敵意も強い為、正しく状況認識ができない。
・また、中国には独自の「天下思想」があり、中国を中心とした強固な世界観がある。
天下思想の下では、世界は中国を中心に回っており、他の国々は(アメリカも含めて)中国の足元にも及ばないという意識が強い。
・歴史的名著である「孫子」等の戦略思想が指導者層に根付いており、「欺瞞」や「策略」によって中国に不利な状況も切り抜けられると思っている。
③独自に組織の利益を追求する中国
・中国人民解放軍は経済成長率にみあった軍拡路線を歩んでおり、一般人民からも支持されている。その為、軍拡路線を止める
事ができない。人民解放軍は共産党の政策に対して大きな影響力を有している。
・また、人民解放軍以外の実行力をもつ下部組織、「漁政」や「海監」(いずれも大型の艦船を保有し中国の領海での利益保護を目的とする政府の組織)等が、自らの組織の拡大のため(中央の意志をそむくような)
横暴な行動を外国に対して行っている。その結果、ますます近隣諸国が警戒を強めている。
④結論と予測
・中国が8%近い経済成長を続ける限りは、パワーの増大に伴う中国の傲慢な行動は続く。
・中国はあらゆる分野で力を急激につけてきている。であるがゆえに、ここでいきなり控えめな対外政策を採用するのは【無理】である。
・中国の急速な経済成長は軍事費の急速な増加を可能にしている。であるがゆえに、軍事費を減らすのは【無理】である。
・人民解放軍が官僚制度の普遍的な性質を克服して、自分たちの縮小を受け入れるのは【無理】である。
・軍が無能であったために恥をかいたという過去があるため、軍事力の一方的な放棄(を受け入れるのは)は、中国の国民の世論には【無理】である。
・中国が核保有国である為「戦争」という手段ではなく、経済的な制裁(燃料や原材料の輸出禁止措置)によって経済成長率を4%程度に落とすことが有効な対策である。
以上、300ページを超える本書の要点をまとめたつもりである。
本書はルトワックの「戦略」思想がベースになっているので、難物である氏の「戦略論」を理解する為の副読本としての価値もあると思う。
気になる方はアマゾンの書評などもご参考に。
http://www.amazon.co.jp/%E8%87%AA%E6%BB%85%E3%81%99%E3%82%8B%E4%B8%AD%E5%9B%BD-%E3%82%A8%E3%83%89%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%83%E3%82%AF/dp/4829505907/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1448788306&sr=8-2&keywords=%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%83%E3%82%AF
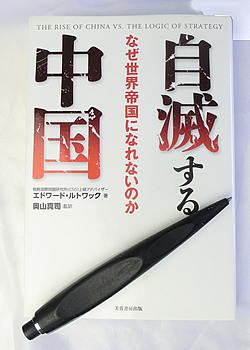
もじゃもじゃです!
今回は反中派の人が泣いて喜びそうなタイトルの本をご紹介。
ただ、この本はバリバリの現役戦略家が書いた戦略本であり、巷にあふれる反中意識を煽るような安易な本ではありません。
著者ルトワック氏は、ワシントンのシンクタンクCSISの上級アドバイザー。
ホワイトハウスの国家安全保障会議のメンバーも務めたこともある文武両道の実務派。
氏自身が中東戦争への従軍経験があり、今でもアドバイザーとして危険な現場へ出向く事もある。
氏の名声は著書「戦略論」によるところが大きく、「戦略論」は世界各国の戦略教育現場で必読書となっている。
さて、本書の内容を簡単にまとめると、
①増大する中国のパワー(経済力・軍事力・国際的発言力)に対する近隣諸国含めた他国の警戒姿勢が強まる。
・中国の年率8%のGDP成長率、ほぼ同じ程度の軍事費の増加を背景に中国は国際的存在感を増してきた。
・2009年までは中国は「平和的に台頭」していたが、2010年の経済危機を境に、他国に対して傲慢な姿勢をあからさまにし始めた。
日本、フィリピン、ベトナムとの施設や領土を巡る紛争。最近では南シナ海の埋め立て問題等。
・この動きに対して米軍の中東から太平洋へのシフト、日本を含む近隣諸国の防衛的協力体制の構築。(例えば、日本がベトナムに資金援助を行いベトナムがロシア製潜水艦を購入、ロシア製潜水艦をすでに使用しているインドが潜水艦経験の浅いベトナムに対して自国の基地を使用した教育を提供)
が行われている。
・オーストラリアは、(経済的に中国への依存度が高いにも関わらず)日本を含め積極的にアジア各国との(対中)連携を強めている。
②その状況を正確に把握できない中国の「大国自閉症」
・中国の傲慢な行動・発言に対して、既に各国から非難の声や態度は明確になっているが、中国はその方針を改めない。
・また国際社会での経験も浅く、外国への敵意も強い為、正しく状況認識ができない。
・また、中国には独自の「天下思想」があり、中国を中心とした強固な世界観がある。
天下思想の下では、世界は中国を中心に回っており、他の国々は(アメリカも含めて)中国の足元にも及ばないという意識が強い。
・歴史的名著である「孫子」等の戦略思想が指導者層に根付いており、「欺瞞」や「策略」によって中国に不利な状況も切り抜けられると思っている。
③独自に組織の利益を追求する中国
・中国人民解放軍は経済成長率にみあった軍拡路線を歩んでおり、一般人民からも支持されている。その為、軍拡路線を止める
事ができない。人民解放軍は共産党の政策に対して大きな影響力を有している。
・また、人民解放軍以外の実行力をもつ下部組織、「漁政」や「海監」(いずれも大型の艦船を保有し中国の領海での利益保護を目的とする政府の組織)等が、自らの組織の拡大のため(中央の意志をそむくような)
横暴な行動を外国に対して行っている。その結果、ますます近隣諸国が警戒を強めている。
④結論と予測
・中国が8%近い経済成長を続ける限りは、パワーの増大に伴う中国の傲慢な行動は続く。
・中国はあらゆる分野で力を急激につけてきている。であるがゆえに、ここでいきなり控えめな対外政策を採用するのは【無理】である。
・中国の急速な経済成長は軍事費の急速な増加を可能にしている。であるがゆえに、軍事費を減らすのは【無理】である。
・人民解放軍が官僚制度の普遍的な性質を克服して、自分たちの縮小を受け入れるのは【無理】である。
・軍が無能であったために恥をかいたという過去があるため、軍事力の一方的な放棄(を受け入れるのは)は、中国の国民の世論には【無理】である。
・中国が核保有国である為「戦争」という手段ではなく、経済的な制裁(燃料や原材料の輸出禁止措置)によって経済成長率を4%程度に落とすことが有効な対策である。
以上、300ページを超える本書の要点をまとめたつもりである。
本書はルトワックの「戦略」思想がベースになっているので、難物である氏の「戦略論」を理解する為の副読本としての価値もあると思う。
気になる方はアマゾンの書評などもご参考に。
http://www.amazon.co.jp/%E8%87%AA%E6%BB%85%E3%81%99%E3%82%8B%E4%B8%AD%E5%9B%BD-%E3%82%A8%E3%83%89%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%83%E3%82%AF/dp/4829505907/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1448788306&sr=8-2&keywords=%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%83%E3%82%AF
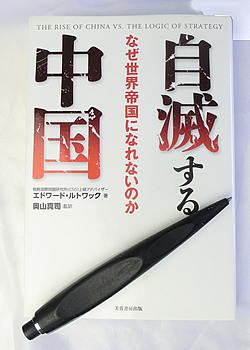
2015年08月15日
大国政治の悲劇 改訂版

三矢史上最も酸っぱいサイダーを毎日飲んでるもじゃもじゃです!
今回は、「大国政治の悲劇 改訂版」ジョン・J・ミアシャイマー著 奥山真司訳 をご紹介します。
サブタイトルは刺激的な「米中は必ず衝突する」
500ページを超える大著ですが、一読の価値ありです。いや、二度、三度と読む価値があると思います。
著者は「イスラエルロビーとアメリカの外交政策」で、数年前に日本でも話題になった人物で、米シカゴ大学の教授。
本書は、「大国」がなぜ戦争を引き起こすのかを、「パワー」という観点から考察し、「オフェンシブ・リアリズム」という理論を提唱しております。
「オフェンシブ・リアリズム」とは、
【「国際システムの基本的な構造によって、国家は安全保障を心配するようになり、互いにパワーを争うようになる」
「すべての大国の究極の目標は世界権力の分け前を最大化することであり、最終的にこのシステムを支配することにある。」
実際の例から見れば、これは「最も強力な国家は、自分のいる地域で覇権を確立しようとする」ということであり、同時に別の地域にあるライバル大国の地域覇権を阻止しようとするということだ。】
本書P481より引用
予備知識なしに、ここだけを読むとフィクションかゲームの話か?と思ってしまいそうですが、本書では歴史的事実と著者の5つの仮説から、淡々とオフェンシブ・リアリズムについて説いております。
オフェンシブ・リアリズムに沿って動いており、かつ現在唯一の「地域」覇権国がアメリカ。
第一次大戦で、ヨーロッパを支配しようとしたドイツを叩き、第二次大戦で同じくドイツとアジアを支配しようとした日本を叩いております。
そして、現在アジアで、覇権国たらんとしているのが中国。
尖閣諸島をはじめ、南シナ海、東シナ海での動きは周知の事実。
改訂版には、「中国は平和的に台頭できるか?」という章が追加されており、500ページがしんどい人はここだけでも読む価値があると思います。
私には本書を論評する知識や洞察力などありませんが、私自身がぼんやりと描いていた世界観に近いため、素直に納得致しました。
興味をお持ちの方は、アマゾンの書評をご参照ください。
対中国という観点だけでなく、「戦争はなぜ起きるのか?」という大いなる疑問をお持ちの方にもお勧め致します。
本書については、また別途ご紹介させて頂きます。
2015年07月02日
現代の軍事戦略入門
蒸し暑いですね~もじゃもじゃです!
さて、前回に引き続き書籍ネタです。
「現代の軍事戦略入門」エリノア・スローン著

「陸海空からサイバー、核、宇宙まで」というサブタイトルが示すとおり、ゲリラ戦まで含めた軍事戦略理論の概要を幅広く知ることができる1冊です。
古典的なマハン,コルベット、ジョミニ等から、まさに現代の戦略まで時間軸も奥行き深く扱っており、しかも各項目をコンパクトにまとめてある為、私のような素人でも読みやすくなっております。
古典的な戦略本(マハン、リデルハート、クラウゼヴッツ等)しか読んだことのない私には、各項目の現代の戦略が新鮮でした。例えば、精密誘導弾の登場によって核戦略の見直しを図るのか否かとか、ゲリラ戦が従来の国家主体の戦略論に見直しを迫るほどの重要性を持つのか?、といったところは個人的に興味深い点でした。
基本的に戦略本なので、兵器についての記述はほとんどありませんが、興味のある方は夏休みの課題図書にいかが?(笑)
さて、前回に引き続き書籍ネタです。
「現代の軍事戦略入門」エリノア・スローン著

「陸海空からサイバー、核、宇宙まで」というサブタイトルが示すとおり、ゲリラ戦まで含めた軍事戦略理論の概要を幅広く知ることができる1冊です。
古典的なマハン,コルベット、ジョミニ等から、まさに現代の戦略まで時間軸も奥行き深く扱っており、しかも各項目をコンパクトにまとめてある為、私のような素人でも読みやすくなっております。
古典的な戦略本(マハン、リデルハート、クラウゼヴッツ等)しか読んだことのない私には、各項目の現代の戦略が新鮮でした。例えば、精密誘導弾の登場によって核戦略の見直しを図るのか否かとか、ゲリラ戦が従来の国家主体の戦略論に見直しを迫るほどの重要性を持つのか?、といったところは個人的に興味深い点でした。
基本的に戦略本なので、兵器についての記述はほとんどありませんが、興味のある方は夏休みの課題図書にいかが?(笑)










