2016年12月07日
「狙撃手」ピーター・ブルックスミス著
もじゃもじゃです!
今回は「狙撃手」ピーター・ブルック著 守真人訳 原書房刊
をご紹介します。
本書は狙撃の入門書的な書籍で、著名な狙撃手から狙撃用ライフルの紹介、狙撃の歴史までを網羅した一冊となっています。訳も平易で読みやすい。
実は本書を読むのは2回目。数年前に一度読んだのだが、20m狙撃をやるようになって、狙撃手に改めて興味が湧いて再び手に取ってみた次第。
今回読んで面白かったのは軍と警察のスナイパーの違いや、スナイパーに適した人格や性格といったところ。
一般の歩兵は自分の放った弾丸が相手を殺す場面を見ることは少ないが、スナイパーはある程度ターゲットについて知ってから、そのターゲットをスコープで拡大してじっくりと見つつ、殺さなければならない。
仕事・任務として「死神」を演じつつ、社会にも適応していかなければならない。しかも自分が行った仕事の結果を一生背負っていかなければならない。
射撃がうまい普通の人が、訓練だけででスナイパーになれるのか?そんな疑問も浮かんできた。
スナイパー関連の書籍をちょっと漁ってみようと思う。
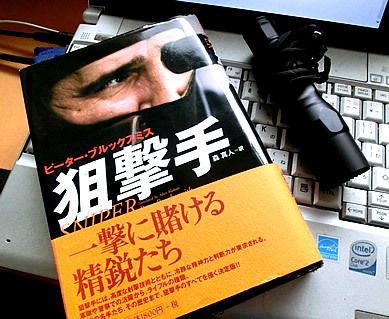
今回は「狙撃手」ピーター・ブルック著 守真人訳 原書房刊
をご紹介します。
本書は狙撃の入門書的な書籍で、著名な狙撃手から狙撃用ライフルの紹介、狙撃の歴史までを網羅した一冊となっています。訳も平易で読みやすい。
実は本書を読むのは2回目。数年前に一度読んだのだが、20m狙撃をやるようになって、狙撃手に改めて興味が湧いて再び手に取ってみた次第。
今回読んで面白かったのは軍と警察のスナイパーの違いや、スナイパーに適した人格や性格といったところ。
一般の歩兵は自分の放った弾丸が相手を殺す場面を見ることは少ないが、スナイパーはある程度ターゲットについて知ってから、そのターゲットをスコープで拡大してじっくりと見つつ、殺さなければならない。
仕事・任務として「死神」を演じつつ、社会にも適応していかなければならない。しかも自分が行った仕事の結果を一生背負っていかなければならない。
射撃がうまい普通の人が、訓練だけででスナイパーになれるのか?そんな疑問も浮かんできた。
スナイパー関連の書籍をちょっと漁ってみようと思う。
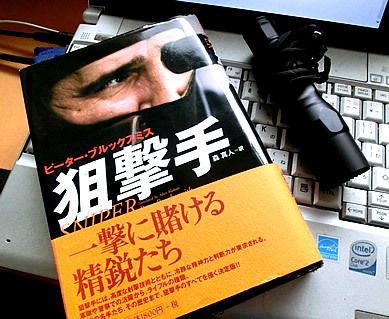
2016年11月29日
「戦略論の名著」孫子、マキャヴェリから現代まで
もじゃもじゃです!
今回は、野中郁次郎編著「戦略論の名著」中公新書刊をご紹介。
野中郁次郎氏はビジネス書としても人気の高い「失敗の本質」で名高い。
「戦略論の名著」は副題に「孫子、マキャヴェリから現代まで」とあるように、古今東西の戦略論の名著12冊の概要を紹介した入門書である。
以前紹介した「名著で学ぶ戦争論」よりも、著書の紹介にページを費やしており(新書で20ページ程度)、解説もより詳しく、万人向けとなっている。
紹介されている12冊は以下のとおり。
①孫武「孫子」 ②マキャヴェリ「君主論」 ③クラウゼヴィッツ「戦争論」 ④マハン「海上権力史論」 ⑤毛沢東「遊撃戦論」 ⑥石原莞爾「戦争史大観」 ⑦リデルハート「戦略論」 ⑧ルトワック「戦略」 ⑨クレフェルト「戦争の変遷」 ⑩グレイ「現代の戦略」 ⑪ノックス&マーレー「軍事革命とRMAの戦略史」 ⑫ドールマン「アストロポリティーク」
⑤⑥⑫を除くと戦略論の定番的な選択とも言える。
戦略論はとかく難しい。理解に歴史的、軍事的、国際政治的背景の知識が必要という根本的な難しさに加えて、文章そのものが読みやすさを前提につくられていないことが多いのも一因である。
例えば⑩グレイ「現代の戦略」など、その最たるものの一つである。
本書「戦略論の名著」では、そんな難解なグレイ「現代の戦略」を、グレイの教え子でもある奥山氏がスパッと本質を解説をしてくれる。解説を念頭に「現代の戦略」を再読することで、枝葉に行かず、より本質の理解が深まる。
もちろん、初読者の為の読書ガイドとしても大いに活用できる。
戦略論に興味のある若い読者に特にお勧めである。

今回は、野中郁次郎編著「戦略論の名著」中公新書刊をご紹介。
野中郁次郎氏はビジネス書としても人気の高い「失敗の本質」で名高い。
「戦略論の名著」は副題に「孫子、マキャヴェリから現代まで」とあるように、古今東西の戦略論の名著12冊の概要を紹介した入門書である。
以前紹介した「名著で学ぶ戦争論」よりも、著書の紹介にページを費やしており(新書で20ページ程度)、解説もより詳しく、万人向けとなっている。
紹介されている12冊は以下のとおり。
①孫武「孫子」 ②マキャヴェリ「君主論」 ③クラウゼヴィッツ「戦争論」 ④マハン「海上権力史論」 ⑤毛沢東「遊撃戦論」 ⑥石原莞爾「戦争史大観」 ⑦リデルハート「戦略論」 ⑧ルトワック「戦略」 ⑨クレフェルト「戦争の変遷」 ⑩グレイ「現代の戦略」 ⑪ノックス&マーレー「軍事革命とRMAの戦略史」 ⑫ドールマン「アストロポリティーク」
⑤⑥⑫を除くと戦略論の定番的な選択とも言える。
戦略論はとかく難しい。理解に歴史的、軍事的、国際政治的背景の知識が必要という根本的な難しさに加えて、文章そのものが読みやすさを前提につくられていないことが多いのも一因である。
例えば⑩グレイ「現代の戦略」など、その最たるものの一つである。
本書「戦略論の名著」では、そんな難解なグレイ「現代の戦略」を、グレイの教え子でもある奥山氏がスパッと本質を解説をしてくれる。解説を念頭に「現代の戦略」を再読することで、枝葉に行かず、より本質の理解が深まる。
もちろん、初読者の為の読書ガイドとしても大いに活用できる。
戦略論に興味のある若い読者に特にお勧めである。

2016年11月14日
「名著で学ぶ戦争論」
もじゃもじゃです!
「名著で学ぶ戦争論」石津朋之編著 日経ビジネス人文庫刊 をご紹介します。
編著者は防衛省防衛研究所 戦史部第1戦史研究室主任研究官であり、各種戦略関連の著書訳書を多く執筆している。
本書は「一般読者が軍事戦略や国家戦略についてより身近に考えるガイド」としてまとめられている。
章立てと紹介されている著者をご紹介する。
第Ⅰ部 古典に学ぶ軍事戦略
・孫子、トゥキディデス、カエサル等
第Ⅱ部 クラウゼヴィッツ「戦争論」に学ぶ
・クラウゼヴィッツ、ハワード、ブロディ等
第Ⅲ部 戦争の哲学に学ぶ
・毛沢東、カント、ガット等
第Ⅳ部 システムとしての戦略論
・リデルハート、マハン、ドゥーエ等
第Ⅴ部 国家と戦争の関係から学ぶ
・フィリップス、デルブリュック、キーガン等
第Ⅵ部 現代の戦略論
・ルトワック、クレフェルト、グレイ等
各章毎に代表的な著作が紹介され、それぞれの著作が2~3ページで概要が分かるようになっており、初心者にとって非常に分かりやすいガイドブックとなっている。
私がご紹介している「現代の軍事戦略」よりも内容は平易であり、かつ幅広い書籍を紹介している。
また、この分野は、どうしても英米系に偏りがちであるが、中国古典や「甲陽軍鑑」、またドイツ系の書籍も紹介されている。
私は7年前に本書を購入したが、今でも時々興味のある章だけを読み返して、次の読書の参考にしている。
残念なのは、訳書が少ないこと。読みたいと思っても、翻訳が出ていない書籍が多いのが惜しい。もっとも翻訳が出ている書籍だけでは、納得のいく読書ガイドは作れないのが現状である。
読書の秋 の為のガイドブックとして、文庫でもあるし、ご一読されてはいかがでしょう?
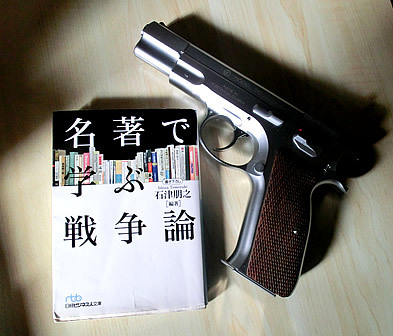
「名著で学ぶ戦争論」石津朋之編著 日経ビジネス人文庫刊 をご紹介します。
編著者は防衛省防衛研究所 戦史部第1戦史研究室主任研究官であり、各種戦略関連の著書訳書を多く執筆している。
本書は「一般読者が軍事戦略や国家戦略についてより身近に考えるガイド」としてまとめられている。
章立てと紹介されている著者をご紹介する。
第Ⅰ部 古典に学ぶ軍事戦略
・孫子、トゥキディデス、カエサル等
第Ⅱ部 クラウゼヴィッツ「戦争論」に学ぶ
・クラウゼヴィッツ、ハワード、ブロディ等
第Ⅲ部 戦争の哲学に学ぶ
・毛沢東、カント、ガット等
第Ⅳ部 システムとしての戦略論
・リデルハート、マハン、ドゥーエ等
第Ⅴ部 国家と戦争の関係から学ぶ
・フィリップス、デルブリュック、キーガン等
第Ⅵ部 現代の戦略論
・ルトワック、クレフェルト、グレイ等
各章毎に代表的な著作が紹介され、それぞれの著作が2~3ページで概要が分かるようになっており、初心者にとって非常に分かりやすいガイドブックとなっている。
私がご紹介している「現代の軍事戦略」よりも内容は平易であり、かつ幅広い書籍を紹介している。
また、この分野は、どうしても英米系に偏りがちであるが、中国古典や「甲陽軍鑑」、またドイツ系の書籍も紹介されている。
私は7年前に本書を購入したが、今でも時々興味のある章だけを読み返して、次の読書の参考にしている。
残念なのは、訳書が少ないこと。読みたいと思っても、翻訳が出ていない書籍が多いのが惜しい。もっとも翻訳が出ている書籍だけでは、納得のいく読書ガイドは作れないのが現状である。
読書の秋 の為のガイドブックとして、文庫でもあるし、ご一読されてはいかがでしょう?
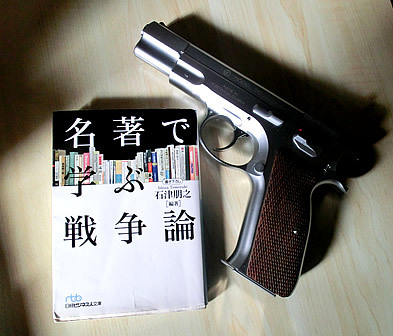
2016年11月06日
「中国はいかに国境を書き換えてきたか」
もじゃもじゃです!
今日は平松茂雄著「中国はいかに国境を書き換えてきたか 地図が語る領土拡張の真実」(草思社)をご紹介します。
本書は毛沢東時代から現代まで、中国がいかに国境線を書き換えてきたかを、豊富な地図類で解説する書である。
著者の平松茂雄氏は、元防衛研究所室長であり、中国の専門家である。
私が感じた本書の面白い点として、
①中国は国境を固定のものとして認識をしていない。
・国力が増大すれば国境線は広がるし、国力が落ちれば狭まる。
②元々「国境」にあたる言葉はなく「辺彊(へんきょう)」がそれにあたる。
・中国にとって南シナ海も東シナ海も「辺彊(へんきょう)」である。
③毛沢東時代から着々と進めて来た南シナ海、東シナ海進出。
・50年以上に渡って南シナ海、東シナ海進出には手を打ってきている。
・そしてその成果は出つつある。
④尖閣だけに目を奪われてはならない。
・日本はとかく尖閣だけに目を奪われがちであるが、中国の本当の目的は南西諸島にある。
・南西諸島は、中国海軍が太平洋に進出する戦略ルート上にある。
⑤弱腰な日本外交
・日本は安倍政権以前は、中国の領土拡張行為に対して、外交上の抗議をするだけであった。
・結果として中国の行為を黙認している。
以上。
本書を読むとルトワックの「チャイナ4.0」への理解も深まると思う。

今日は平松茂雄著「中国はいかに国境を書き換えてきたか 地図が語る領土拡張の真実」(草思社)をご紹介します。
本書は毛沢東時代から現代まで、中国がいかに国境線を書き換えてきたかを、豊富な地図類で解説する書である。
著者の平松茂雄氏は、元防衛研究所室長であり、中国の専門家である。
私が感じた本書の面白い点として、
①中国は国境を固定のものとして認識をしていない。
・国力が増大すれば国境線は広がるし、国力が落ちれば狭まる。
②元々「国境」にあたる言葉はなく「辺彊(へんきょう)」がそれにあたる。
・中国にとって南シナ海も東シナ海も「辺彊(へんきょう)」である。
③毛沢東時代から着々と進めて来た南シナ海、東シナ海進出。
・50年以上に渡って南シナ海、東シナ海進出には手を打ってきている。
・そしてその成果は出つつある。
④尖閣だけに目を奪われてはならない。
・日本はとかく尖閣だけに目を奪われがちであるが、中国の本当の目的は南西諸島にある。
・南西諸島は、中国海軍が太平洋に進出する戦略ルート上にある。
⑤弱腰な日本外交
・日本は安倍政権以前は、中国の領土拡張行為に対して、外交上の抗議をするだけであった。
・結果として中国の行為を黙認している。
以上。
本書を読むとルトワックの「チャイナ4.0」への理解も深まると思う。

2016年10月22日
「現代の軍事戦略」新しい戦争
もじゃもじゃです!
「現代の軍事戦略入門」
(エリノア・スローン著 奥山真司、関根大介訳)
本書は、軍事戦略理論を古典から現代までコンパクトにまとめられてお り、軍事戦略の変遷を一般の読者でも理解できる入門書です。
なかなか知ることのできない、現代の戦略理論に重点が置かれている一方、基礎となった古典的理論にも、目配りされております。
「新しい戦争」とは、ユーゴスラビア内戦やその他の地域で行われた内戦や紛争の解決に対して、国際社会が直面した困難を受けて使われるようになった用語。ゲリラ戦略の締めくくりとして、「新しい戦争」論者と対反乱戦の理論についてご紹介します。
■「新戦争論」メアリー・カルドー
・著書「新戦争論」1999年刊
・1990年代のアフリカや東欧で登場した組織的な暴力の、戦い方や目的や手段が「新しい形の戦争である」と論じた。
・クレフェルトと同じように、「新しい戦争」が「国家の統治能力の消耗、国家の崩壊」という文脈から生じている。
・冷戦の地政学的、イデオロギー的な目的の代わりに、新しい戦争では「アイデンティティー・ポリティックス」つまり、特定の民族、部族、もしくは言語的なアイデンティティを基盤にした権力闘争が行われるようになった。
・「新しい戦争」は、別のアイデンティティーを持った人間を全て排除することによって政治的コントロールを獲得しようとするものであり、これは住民の追放や強制移住、そして大量虐殺などの手段を通じて行われる。この現象は「民族浄化」という言葉によって広く知られるようになった。
■ルパート・スミス
・NATO軍のアライドフォース作戦時の副最高司令官。
・著書「ルパート・スミス 軍事力の効用:新時代 戦争論」2005年刊
・工業化した国家同士が戦う「対称的な戦争」から、「軍同士が交戦するような戦場が存在しなかったり、すべての交戦者の中に必ずしも軍隊が含まれるわけではないという事実が反映された、人間戦争」へとシフトしたと論じた。
・「街や家や畑にいる市民たちがすべて あらゆるところにいるすべての人間が 戦場であるという現実」
・(紛争に介入する)NATOのような戦う組織の目的が、「政治的な成果を決定できる具体的な目標の奪取から、成果を決定する条件を作り出すことへと変化している」
・このような条件をどのように作るべきかは、当時から現在までも答えは出ていない。
■デビッド・キルカレン
・オーストラリア軍の中佐。ペンタゴンでも対反乱のアドバイスを行う。
・冷戦後の反乱の特徴は、革命的な目標やその質にあると指摘。
・反乱の古典的理論では、一国の中の非国家主体と政府の間で発生し、その最終目的は国家の支配を勝ち取るとろこにあると想定して扱われてきたが、現在の反乱の多くは、ただ単に国家を破壊しようとするだけであり、統治権を奪取するところまでは狙われていない。
・「偶発的なゲリラ」よそからやって来た過激主義者と現地住民が親密になって、ついには地元住民が武器をとって過激主義者と一緒に戦う「偶発的な」ゲリラになってしまう、感染症のような4つのプロセスを提示。
■FM3-24 ペトレイアス
・元米陸軍大将。
・アメリカの対反乱ドクトリン「米陸軍・海兵隊対反乱野外教令」(通称FM3-24)を2006年に発行。
・FM3-24は古典的な対反乱アプローチが支配的。特に注目を集めたのはパラドックスの部分。発行当時は非効率的な殺傷的アプローチが支配的だった為。
パラドックスとは、例えば・・・
「部隊を防護しようとすると、ますます安全ではなくなることがある」⇒軍の部隊の安全を確保しようとして部隊を宿営地の中に留め、住民の中に入っていかせないと、作戦の成功に必要な情報に触れるチャンスが減少してしまう。
「軍事力を使えば使うほど効果が薄れていくことがある」⇒軍事力を行使すればするほど付随的被害や間違いが発生しやすくなり、反乱勢力のプロパガンダに使われる材料が増えることになる。
「対反乱作戦が成功するほど、使用できる武力が少なくなり、容認すべきリスクも増加することになる」⇒対反乱作戦が進展するにつれて、警察的な任務の方が増え、兵員はより厳しい交戦規定に従わなくてはならず、より大きなリスクが対反乱に伴うことになる。
・また、「現地住民の安全確保」は対反乱の中心的な教訓とされた。

「現代の軍事戦略」のご紹介は今回で一旦終了します。「サイバー戦略」「核戦略」「スペースパワー」については、時機を見て掲載の予定。
本ブログをきっかけに一人でも、本書を含めた戦略書類を手に取って頂き、平和や戦争への理解を一緒に深めてくれると嬉しく思います。
「現代の軍事戦略入門」
(エリノア・スローン著 奥山真司、関根大介訳)
本書は、軍事戦略理論を古典から現代までコンパクトにまとめられてお り、軍事戦略の変遷を一般の読者でも理解できる入門書です。
なかなか知ることのできない、現代の戦略理論に重点が置かれている一方、基礎となった古典的理論にも、目配りされております。
「新しい戦争」とは、ユーゴスラビア内戦やその他の地域で行われた内戦や紛争の解決に対して、国際社会が直面した困難を受けて使われるようになった用語。ゲリラ戦略の締めくくりとして、「新しい戦争」論者と対反乱戦の理論についてご紹介します。
■「新戦争論」メアリー・カルドー
・著書「新戦争論」1999年刊
・1990年代のアフリカや東欧で登場した組織的な暴力の、戦い方や目的や手段が「新しい形の戦争である」と論じた。
・クレフェルトと同じように、「新しい戦争」が「国家の統治能力の消耗、国家の崩壊」という文脈から生じている。
・冷戦の地政学的、イデオロギー的な目的の代わりに、新しい戦争では「アイデンティティー・ポリティックス」つまり、特定の民族、部族、もしくは言語的なアイデンティティを基盤にした権力闘争が行われるようになった。
・「新しい戦争」は、別のアイデンティティーを持った人間を全て排除することによって政治的コントロールを獲得しようとするものであり、これは住民の追放や強制移住、そして大量虐殺などの手段を通じて行われる。この現象は「民族浄化」という言葉によって広く知られるようになった。
■ルパート・スミス
・NATO軍のアライドフォース作戦時の副最高司令官。
・著書「ルパート・スミス 軍事力の効用:新時代 戦争論」2005年刊
・工業化した国家同士が戦う「対称的な戦争」から、「軍同士が交戦するような戦場が存在しなかったり、すべての交戦者の中に必ずしも軍隊が含まれるわけではないという事実が反映された、人間戦争」へとシフトしたと論じた。
・「街や家や畑にいる市民たちがすべて あらゆるところにいるすべての人間が 戦場であるという現実」
・(紛争に介入する)NATOのような戦う組織の目的が、「政治的な成果を決定できる具体的な目標の奪取から、成果を決定する条件を作り出すことへと変化している」
・このような条件をどのように作るべきかは、当時から現在までも答えは出ていない。
■デビッド・キルカレン
・オーストラリア軍の中佐。ペンタゴンでも対反乱のアドバイスを行う。
・冷戦後の反乱の特徴は、革命的な目標やその質にあると指摘。
・反乱の古典的理論では、一国の中の非国家主体と政府の間で発生し、その最終目的は国家の支配を勝ち取るとろこにあると想定して扱われてきたが、現在の反乱の多くは、ただ単に国家を破壊しようとするだけであり、統治権を奪取するところまでは狙われていない。
・「偶発的なゲリラ」よそからやって来た過激主義者と現地住民が親密になって、ついには地元住民が武器をとって過激主義者と一緒に戦う「偶発的な」ゲリラになってしまう、感染症のような4つのプロセスを提示。
■FM3-24 ペトレイアス
・元米陸軍大将。
・アメリカの対反乱ドクトリン「米陸軍・海兵隊対反乱野外教令」(通称FM3-24)を2006年に発行。
・FM3-24は古典的な対反乱アプローチが支配的。特に注目を集めたのはパラドックスの部分。発行当時は非効率的な殺傷的アプローチが支配的だった為。
パラドックスとは、例えば・・・
「部隊を防護しようとすると、ますます安全ではなくなることがある」⇒軍の部隊の安全を確保しようとして部隊を宿営地の中に留め、住民の中に入っていかせないと、作戦の成功に必要な情報に触れるチャンスが減少してしまう。
「軍事力を使えば使うほど効果が薄れていくことがある」⇒軍事力を行使すればするほど付随的被害や間違いが発生しやすくなり、反乱勢力のプロパガンダに使われる材料が増えることになる。
「対反乱作戦が成功するほど、使用できる武力が少なくなり、容認すべきリスクも増加することになる」⇒対反乱作戦が進展するにつれて、警察的な任務の方が増え、兵員はより厳しい交戦規定に従わなくてはならず、より大きなリスクが対反乱に伴うことになる。
・また、「現地住民の安全確保」は対反乱の中心的な教訓とされた。

「現代の軍事戦略」のご紹介は今回で一旦終了します。「サイバー戦略」「核戦略」「スペースパワー」については、時機を見て掲載の予定。
本ブログをきっかけに一人でも、本書を含めた戦略書類を手に取って頂き、平和や戦争への理解を一緒に深めてくれると嬉しく思います。
2016年10月19日
ルトワック氏来日 TV出演!
もじゃもじゃです!
ベストセラーとなった「中国(チャイナ)4.0」の著者であるE・ルトワック氏が来日中。
「中国(チャイナ)4.0」はルトワック氏に、国際政治学者の奥山氏がインタビュー形式で聞き取ったものを書籍化したもの。
同じ形式で続編『中国5.0』(仮)を来年出版予定とのこと。要約版が来月「日本の論点」に掲載予定らしい。
また、10月21日夜BSフジの「プライムニュース」にご出演の予定。
「中国(チャイナ)4.0」は本ブログでもご紹介(その1、その2)したことがありますので、ご興味のある方はご覧ください。
ここのところ「現代の軍事戦略」ばかりをご紹介してきましたが、次回以降中国の南シナ海進出等時事問題についても取り上げていく予定です。

ベストセラーとなった「中国(チャイナ)4.0」の著者であるE・ルトワック氏が来日中。
「中国(チャイナ)4.0」はルトワック氏に、国際政治学者の奥山氏がインタビュー形式で聞き取ったものを書籍化したもの。
同じ形式で続編『中国5.0』(仮)を来年出版予定とのこと。要約版が来月「日本の論点」に掲載予定らしい。
また、10月21日夜BSフジの「プライムニュース」にご出演の予定。
「中国(チャイナ)4.0」は本ブログでもご紹介(その1、その2)したことがありますので、ご興味のある方はご覧ください。
ここのところ「現代の軍事戦略」ばかりをご紹介してきましたが、次回以降中国の南シナ海進出等時事問題についても取り上げていく予定です。

2016年10月06日
現代の軍事戦略 ゲリラ戦の理論 ~冷戦以降
もじゃもじゃです!
「現代の軍事戦略入門」
(エリノア・スローン著 奥山真司、関根大介訳)
本書は、軍事戦略理論を古典から現代までコンパクトにまとめられてお り、軍事戦略の変遷を一般の読者でも理解できる入門書です。
なかなか知ることのできない、現代の戦略理論に重点が置かれている一方、基礎となった古典的理論にも、目配りされております。
さて、今回は「ゲリラ戦の理論 ~冷戦後」としまして、クレピネビッチ、ファン・クレフェルト、リンド、ハメスを紹介します。
■アンドリュー・クレピネビッチの反乱、対反乱作戦
・本ブログの「ランドパワーの理論 現代編」でもご紹介した、アンドリュー・クレピネビッチ(米陸軍退役中佐)は、「米陸軍とベトナム」(1986年刊)の中で、「米軍はベトナム戦争の本質をとらえることに失敗した」と正面から指摘した最初の人物の一人。
・対反乱作戦では現地住民の「心と信頼をつかむ」ことが重要であり、その為には政府の多くの機関の協力が必要であり、軍はその中のたった一つの機関に過ぎない。
・クレピネビッチの功績は、2010年代には一般的であるが、1986年時点では注目されていなかった下記の事柄を指摘した点にある。
①反乱・対反乱戦が通常戦とは大きく異なるものであること。
②米陸軍が対反乱で戦えるよう訓練・組織化されていなかったこ と。
③米陸軍が将来最も直面しそうなのは、低強度戦や対反乱戦であ ること。
■現代3大軍事戦略家 マーチン・ファン・クレフェルト
・グレイ、ルトワックと共に現代の3大軍事戦略家の一人。エルサ レム大学の学者。
・将来の戦争は国家主体ではなく、非国家主体の戦争になると指摘。クラウゼヴィッツ的な世界観による三位一体戦争(国家+国民+軍隊)というのは、「戦争は主に国家、厳密にいえば政府により行われるもの」という前提であったが、この時代は終わりをつげ、「非三位一体型」、もしくは「ポスト・クラウゼヴィッツ式」の戦いに取って代わられつつある。
■リンドの第四世代戦
・非三位一体式戦争の視点から第四世代戦を提唱。近代史における戦争は、三つの特徴的な「世代」を経て発展してきており、現代は「第四世代」にうつりつつある。
・「第四世代」は、戦場におけるさらなる分散化、作戦の速度とテンポの向上、集中化された兵站への依存度の低下、機動と分散のさらなる強調、小規模でより機敏な部隊、はっきりした前線や戦線のない「非線形」な戦い、統合作戦への依存度の増加といった要因によって特徴づけられる。
・非国家主体による「第四世代戦」の指標として、「敵の前線から後方への焦点の移動」と「敵の強みをそのまま対抗手段として使う」の2点がある。「敵の前線から後方への焦点の移動」は、非国家主体のテロリストは、直接敵軍隊を戦うのではなく、その後方(敵軍隊の母国)にいる一般人をターゲットとするということ。「敵の強みをそのまま対抗手段として使う」とは、敵(主に西側自由諸国)の社会の自由とオープンさを利用し、その社会に入り込み直接破壊活動を行ったり、ネットやテレビのニュースを使って心理戦を仕掛けたり、麻薬を密輸入したりということ。
■ハメス
・元米海兵隊大佐。著書に「投石器と石:二十一世紀の戦争論」2004年刊。
・第四世代戦は反乱の発展形。
第四世代戦とは「政治、経済、社会、そして軍事など使用可能なネットワークをすべて使って、敵の政策決定者に対して、彼らの戦略目標は達成不可能であったり、獲得可能な利益はコストがかかりすぎるものである、と信じ込ませることにある。」
以上。
次回「新しい戦争学派」に続きます。

「現代の軍事戦略」をご紹介することで軍事、戦略への理解を深め、複雑な国際情勢をマスコミ等に踊らされることなく、自身で考える一助にしたいと思ってます。
また、本ブログをきっかけに一人でも、本書を含めた戦略書を手に取って頂き、平和や戦争への理解を一緒に深めてくれるとなお嬉しく思います。
「現代の軍事戦略入門」
(エリノア・スローン著 奥山真司、関根大介訳)
本書は、軍事戦略理論を古典から現代までコンパクトにまとめられてお り、軍事戦略の変遷を一般の読者でも理解できる入門書です。
なかなか知ることのできない、現代の戦略理論に重点が置かれている一方、基礎となった古典的理論にも、目配りされております。
さて、今回は「ゲリラ戦の理論 ~冷戦後」としまして、クレピネビッチ、ファン・クレフェルト、リンド、ハメスを紹介します。
■アンドリュー・クレピネビッチの反乱、対反乱作戦
・本ブログの「ランドパワーの理論 現代編」でもご紹介した、アンドリュー・クレピネビッチ(米陸軍退役中佐)は、「米陸軍とベトナム」(1986年刊)の中で、「米軍はベトナム戦争の本質をとらえることに失敗した」と正面から指摘した最初の人物の一人。
・対反乱作戦では現地住民の「心と信頼をつかむ」ことが重要であり、その為には政府の多くの機関の協力が必要であり、軍はその中のたった一つの機関に過ぎない。
・クレピネビッチの功績は、2010年代には一般的であるが、1986年時点では注目されていなかった下記の事柄を指摘した点にある。
①反乱・対反乱戦が通常戦とは大きく異なるものであること。
②米陸軍が対反乱で戦えるよう訓練・組織化されていなかったこ と。
③米陸軍が将来最も直面しそうなのは、低強度戦や対反乱戦であ ること。
■現代3大軍事戦略家 マーチン・ファン・クレフェルト
・グレイ、ルトワックと共に現代の3大軍事戦略家の一人。エルサ レム大学の学者。
・将来の戦争は国家主体ではなく、非国家主体の戦争になると指摘。クラウゼヴィッツ的な世界観による三位一体戦争(国家+国民+軍隊)というのは、「戦争は主に国家、厳密にいえば政府により行われるもの」という前提であったが、この時代は終わりをつげ、「非三位一体型」、もしくは「ポスト・クラウゼヴィッツ式」の戦いに取って代わられつつある。
■リンドの第四世代戦
・非三位一体式戦争の視点から第四世代戦を提唱。近代史における戦争は、三つの特徴的な「世代」を経て発展してきており、現代は「第四世代」にうつりつつある。
・「第四世代」は、戦場におけるさらなる分散化、作戦の速度とテンポの向上、集中化された兵站への依存度の低下、機動と分散のさらなる強調、小規模でより機敏な部隊、はっきりした前線や戦線のない「非線形」な戦い、統合作戦への依存度の増加といった要因によって特徴づけられる。
・非国家主体による「第四世代戦」の指標として、「敵の前線から後方への焦点の移動」と「敵の強みをそのまま対抗手段として使う」の2点がある。「敵の前線から後方への焦点の移動」は、非国家主体のテロリストは、直接敵軍隊を戦うのではなく、その後方(敵軍隊の母国)にいる一般人をターゲットとするということ。「敵の強みをそのまま対抗手段として使う」とは、敵(主に西側自由諸国)の社会の自由とオープンさを利用し、その社会に入り込み直接破壊活動を行ったり、ネットやテレビのニュースを使って心理戦を仕掛けたり、麻薬を密輸入したりということ。
■ハメス
・元米海兵隊大佐。著書に「投石器と石:二十一世紀の戦争論」2004年刊。
・第四世代戦は反乱の発展形。
第四世代戦とは「政治、経済、社会、そして軍事など使用可能なネットワークをすべて使って、敵の政策決定者に対して、彼らの戦略目標は達成不可能であったり、獲得可能な利益はコストがかかりすぎるものである、と信じ込ませることにある。」
以上。
次回「新しい戦争学派」に続きます。

「現代の軍事戦略」をご紹介することで軍事、戦略への理解を深め、複雑な国際情勢をマスコミ等に踊らされることなく、自身で考える一助にしたいと思ってます。
また、本ブログをきっかけに一人でも、本書を含めた戦略書を手に取って頂き、平和や戦争への理解を一緒に深めてくれるとなお嬉しく思います。
2016年09月21日
現代の軍事戦略 ゲリラ戦の理論 ~冷戦期
もじゃもじゃです!
「現代の軍事戦略入門」
(エリノア・スローン著 奥山真司、関根大介訳)
本書は、軍事戦略理論を古典から現代までコンパクトにまとめられてお り、軍事戦略の変遷を一般の読者でも理解できる入門書です。
なかなか知ることのできない、現代の戦略理論に重点が置かれている一方、基礎となった古典的理論にも、目配りされております。
さて、今回は冷戦期のゲリラ戦の理論として、ガルーラとトンプソンをご紹介します。
前回のロレンス、毛沢東が、反乱側の理論だったのに対して、ガルーラとトンプソンは仏・英という植民地を支配する側からの視点から「対反乱」についての理論を提唱しています。
■ガルーラの対反乱作戦
・ダヴィド・ガルーラはフランス軍士官として、1950年代にアルジェリア戦争で戦った経験を持つ。
・著書「対反乱作戦:理論と実践」(1964年刊)の中で、対反乱の原則と具体的な行動指針を記している。
・「第一の法則」
対反乱側には地元住民からの支持が(反乱側と同じように)、必須である。反乱側勢力を武力で排除することは難しくないが、排除した後の状態を維持するには、住民の支持がなくてはならない。
・「第二の法則」
住民からの支持の獲得を中心としたもの。「単に同情や承認を得るだけでなく、反乱勢力に対する戦闘への積極的な参加をいかに得るかだ」
・「第三の法則」
(協力してくれる)住民に対する(反乱側の)報復の脅威を解消するためには、反乱勢力や彼らの政治組織に対する軍・警察の作戦の成功が必須である。住民の安全が第一に確保されなければならない。
・「第四の法則」
(ガルーラが著書に記した)手段や作戦は、徹底的かつ長期に渡るものでなければならない。
国全体で一気に実施することはできないとしても、地域ごとに連続して実行されなければならないのである。
これは近年になって「油のシミ」アプローチとして知られるようになっている。

■トンプソンの対反乱作戦
・英空軍士官。50年代のマラヤ、65年以前のベトナムでの実戦経験がある。
・著書「共産主義反乱の打倒」(1965年刊)の中で、問題の解決は、治安維持の手段だけでなく、反乱に関わるあらゆる政治、社会、経済を含めた全般的な計画の文脈の中で考えるべきものであると主張。これは、現在の「政府全体」「包括的な」アプローチに似たもの。
・「ゲリラを国内法の保護の外で対処したいという誘惑は大きいが、それでも対反乱作戦はあくまで法の下で実行すべきである」
これができなければ、支配を再確立しようとする政府の長期的な正統性(レジティマシー)が崩れてしまう。
・トンプソンもガルーラと同様に、対反乱の主要なターゲットは住民であるとしている。また、「油のシミ」アプローチは人口や経済活動の多い都市部から始めていくべきとしている。

次回は冷戦後のゲリラ戦の理論として、1980年代から多く出てきた「反乱、対反乱」「新しい戦争」についてご紹介します。
「現代の軍事戦略」をご紹介することで軍事、戦略への理解を深め、複雑な国際情勢をマスコミ等に踊らされることなく、自身で考える一助にしたいと思ってます。
また、本ブログをきっかけに一人でも、本書を含めた戦略書を手に取って頂き、平和や戦争への理解を一緒に深めてくれるとなお嬉しく思います。
「現代の軍事戦略入門」
(エリノア・スローン著 奥山真司、関根大介訳)
本書は、軍事戦略理論を古典から現代までコンパクトにまとめられてお り、軍事戦略の変遷を一般の読者でも理解できる入門書です。
なかなか知ることのできない、現代の戦略理論に重点が置かれている一方、基礎となった古典的理論にも、目配りされております。
さて、今回は冷戦期のゲリラ戦の理論として、ガルーラとトンプソンをご紹介します。
前回のロレンス、毛沢東が、反乱側の理論だったのに対して、ガルーラとトンプソンは仏・英という植民地を支配する側からの視点から「対反乱」についての理論を提唱しています。
■ガルーラの対反乱作戦
・ダヴィド・ガルーラはフランス軍士官として、1950年代にアルジェリア戦争で戦った経験を持つ。
・著書「対反乱作戦:理論と実践」(1964年刊)の中で、対反乱の原則と具体的な行動指針を記している。
・「第一の法則」
対反乱側には地元住民からの支持が(反乱側と同じように)、必須である。反乱側勢力を武力で排除することは難しくないが、排除した後の状態を維持するには、住民の支持がなくてはならない。
・「第二の法則」
住民からの支持の獲得を中心としたもの。「単に同情や承認を得るだけでなく、反乱勢力に対する戦闘への積極的な参加をいかに得るかだ」
・「第三の法則」
(協力してくれる)住民に対する(反乱側の)報復の脅威を解消するためには、反乱勢力や彼らの政治組織に対する軍・警察の作戦の成功が必須である。住民の安全が第一に確保されなければならない。
・「第四の法則」
(ガルーラが著書に記した)手段や作戦は、徹底的かつ長期に渡るものでなければならない。
国全体で一気に実施することはできないとしても、地域ごとに連続して実行されなければならないのである。
これは近年になって「油のシミ」アプローチとして知られるようになっている。

■トンプソンの対反乱作戦
・英空軍士官。50年代のマラヤ、65年以前のベトナムでの実戦経験がある。
・著書「共産主義反乱の打倒」(1965年刊)の中で、問題の解決は、治安維持の手段だけでなく、反乱に関わるあらゆる政治、社会、経済を含めた全般的な計画の文脈の中で考えるべきものであると主張。これは、現在の「政府全体」「包括的な」アプローチに似たもの。
・「ゲリラを国内法の保護の外で対処したいという誘惑は大きいが、それでも対反乱作戦はあくまで法の下で実行すべきである」
これができなければ、支配を再確立しようとする政府の長期的な正統性(レジティマシー)が崩れてしまう。
・トンプソンもガルーラと同様に、対反乱の主要なターゲットは住民であるとしている。また、「油のシミ」アプローチは人口や経済活動の多い都市部から始めていくべきとしている。

次回は冷戦後のゲリラ戦の理論として、1980年代から多く出てきた「反乱、対反乱」「新しい戦争」についてご紹介します。
「現代の軍事戦略」をご紹介することで軍事、戦略への理解を深め、複雑な国際情勢をマスコミ等に踊らされることなく、自身で考える一助にしたいと思ってます。
また、本ブログをきっかけに一人でも、本書を含めた戦略書を手に取って頂き、平和や戦争への理解を一緒に深めてくれるとなお嬉しく思います。
2016年09月09日
「現代の軍事戦略入門」 ゲリラ戦の理論 古典編
もじゃもじゃです!
「現代の軍事戦略入門」
(エリノア・スローン著 奥山真司、関根大介訳)
本書は、軍事戦略理論を古典から現代までコンパクトにまとめてお
り、軍事戦略の変遷を一般の読者でも理解できる入門書です。
なかなか知ることのできない、現代の戦略理論に重点が置かれてい
る一方、基礎となった古典的理論にも、目配りされております。
さて、今回は「ゲリラ戦の理論」の古典編。
タイトルは「ゲリラ」だが、実質的に内容は「非正規戦の理論」と
なります。
「非正規戦」とは、敵対する国家の組織的な軍隊同士による「通常戦」や「正規戦」ではない、ということ。少なくとも一方が「非国家主体」であることが前提となるタイプの戦いである。
非正規戦の理論の古典としてご紹介するのは、コールウェル、(ア
ラビア)のロレンス、毛沢東である。
■植民地戦争におけるクラウゼヴィッツ C.E.コールウェル
・英陸軍大佐。1880年代から1890年代にかけて、アフガニスタン、
クレタ島、南アフリカで実戦に参加。
・「小規模戦争:原則と実践」という著書で、非国家主体の敵との
戦いの一般法則を、正規軍(対反乱)の視点から、確立すべく試み
た。
・コールウェルの格言の多くは、「小規模戦争」の軍事作戦における多くの戦術レベルの要素、補給や情報に至るまで詳細に触れられており、時を超えて有益性が実証されてきた。
・しかし、反乱勢力を物理的に排除する手段に集中しすぎていた。
■反乱とローレンスの思想
・アラビアのロレンスとして有名な英陸軍士官。
・オスマン・トルコの支配に対するアラブ反乱(1916年~1918年)にアラブ側の遊牧民たちと行動を共にし、「知恵の七柱」という著書で反乱側からの視点でその実践と本質を書き残す。
・大きな特徴としては、敵の殲滅よりも現地住民の支援を重視していた。「活動的なのはたった2%だけだとしても、あとは行動を裏切らないよう黙って支持を与えてくれる友好的な住民の存在。」が必要だと書き残している。
「ある一地方の住民に自由という”我々の理想のために死ぬ”ことを教えることができれば、その地方をものにすることができよう。敵がいるかいないかは二次的な問題にすぎない。」
・また反乱勢力の参加者個々の重要性を特筆しており、彼らを集団として見るのではなく個々の人間として見るべきだとしている。
・戦術については、「軽打してすぐに逃げる(tip and run)」であるべきとし、最小規模の部隊を最も遠い場所で最も迅速に使用するべきだと主張。そして、戦術的には迅速でも、戦いそのものは長期にわたって続け、敵の消耗を通じて勝利を狙うべきだとしている。

■毛沢東の反乱についての思想
・中華人民共和国の建国者。「反乱側」の視点から、革命戦争の基礎文献「遊撃戦論」を著した。
・革命戦争とは、国内で発生し、武力によって政治権力を奪うことを意味している。
・革命戦争の3つの「段階」。国際的に、革命戦争の進行状態を示すのに使われている。
①隔離された地域で根拠地を確立し、そこの住民を革命戦争に参加するよう説得する。
②敵に対する限定的な武力行使。テロリズムやサボタージュの戦術使用を含む。
③ゲリラ部隊をより伝統的な軍隊組織へと変化させ、通常の戦闘によって敵軍と交戦できるようにする。
・住民からの支持を重視。「民衆は水でゲリラは魚であり、この魚は水の外では生きていけない。」
・実際の作戦に関しては、敵が進軍してくるときには撤退し、止まった時に嫌がらせを行い、敵が疲れたときに攻撃を行い、敵が撤退したときに追撃するという、孫子の影響を受けている。
・ロレンスと同じく数年に渡る長期持久戦を想定。「ゲリラ戦では”決戦”などというものは存在しない」
以上、次回は冷戦期の「対植民地・対反乱の理論」についてご紹介予定です。
本書をご紹介することで軍事戦略への理解を深め、複雑な国際情勢をマスコミ等に踊らされることなく、自身で考える一助にしたいと思ってます。
また、本ブログをきっかけに一人でも、本書を含めた戦略書を手に取って頂き、平和や戦争への理解を一緒に深めてくれるとなお嬉しく思います。
「現代の軍事戦略入門」
(エリノア・スローン著 奥山真司、関根大介訳)
本書は、軍事戦略理論を古典から現代までコンパクトにまとめてお
り、軍事戦略の変遷を一般の読者でも理解できる入門書です。
なかなか知ることのできない、現代の戦略理論に重点が置かれてい
る一方、基礎となった古典的理論にも、目配りされております。
さて、今回は「ゲリラ戦の理論」の古典編。
タイトルは「ゲリラ」だが、実質的に内容は「非正規戦の理論」と
なります。
「非正規戦」とは、敵対する国家の組織的な軍隊同士による「通常戦」や「正規戦」ではない、ということ。少なくとも一方が「非国家主体」であることが前提となるタイプの戦いである。
非正規戦の理論の古典としてご紹介するのは、コールウェル、(ア
ラビア)のロレンス、毛沢東である。
■植民地戦争におけるクラウゼヴィッツ C.E.コールウェル
・英陸軍大佐。1880年代から1890年代にかけて、アフガニスタン、
クレタ島、南アフリカで実戦に参加。
・「小規模戦争:原則と実践」という著書で、非国家主体の敵との
戦いの一般法則を、正規軍(対反乱)の視点から、確立すべく試み
た。
・コールウェルの格言の多くは、「小規模戦争」の軍事作戦における多くの戦術レベルの要素、補給や情報に至るまで詳細に触れられており、時を超えて有益性が実証されてきた。
・しかし、反乱勢力を物理的に排除する手段に集中しすぎていた。
■反乱とローレンスの思想
・アラビアのロレンスとして有名な英陸軍士官。
・オスマン・トルコの支配に対するアラブ反乱(1916年~1918年)にアラブ側の遊牧民たちと行動を共にし、「知恵の七柱」という著書で反乱側からの視点でその実践と本質を書き残す。
・大きな特徴としては、敵の殲滅よりも現地住民の支援を重視していた。「活動的なのはたった2%だけだとしても、あとは行動を裏切らないよう黙って支持を与えてくれる友好的な住民の存在。」が必要だと書き残している。
「ある一地方の住民に自由という”我々の理想のために死ぬ”ことを教えることができれば、その地方をものにすることができよう。敵がいるかいないかは二次的な問題にすぎない。」
・また反乱勢力の参加者個々の重要性を特筆しており、彼らを集団として見るのではなく個々の人間として見るべきだとしている。
・戦術については、「軽打してすぐに逃げる(tip and run)」であるべきとし、最小規模の部隊を最も遠い場所で最も迅速に使用するべきだと主張。そして、戦術的には迅速でも、戦いそのものは長期にわたって続け、敵の消耗を通じて勝利を狙うべきだとしている。

■毛沢東の反乱についての思想
・中華人民共和国の建国者。「反乱側」の視点から、革命戦争の基礎文献「遊撃戦論」を著した。
・革命戦争とは、国内で発生し、武力によって政治権力を奪うことを意味している。
・革命戦争の3つの「段階」。国際的に、革命戦争の進行状態を示すのに使われている。
①隔離された地域で根拠地を確立し、そこの住民を革命戦争に参加するよう説得する。
②敵に対する限定的な武力行使。テロリズムやサボタージュの戦術使用を含む。
③ゲリラ部隊をより伝統的な軍隊組織へと変化させ、通常の戦闘によって敵軍と交戦できるようにする。
・住民からの支持を重視。「民衆は水でゲリラは魚であり、この魚は水の外では生きていけない。」
・実際の作戦に関しては、敵が進軍してくるときには撤退し、止まった時に嫌がらせを行い、敵が疲れたときに攻撃を行い、敵が撤退したときに追撃するという、孫子の影響を受けている。
・ロレンスと同じく数年に渡る長期持久戦を想定。「ゲリラ戦では”決戦”などというものは存在しない」
以上、次回は冷戦期の「対植民地・対反乱の理論」についてご紹介予定です。
本書をご紹介することで軍事戦略への理解を深め、複雑な国際情勢をマスコミ等に踊らされることなく、自身で考える一助にしたいと思ってます。
また、本ブログをきっかけに一人でも、本書を含めた戦略書を手に取って頂き、平和や戦争への理解を一緒に深めてくれるとなお嬉しく思います。
2016年08月25日
「現代の軍事戦略入門」エアパワー現代編 その2
もじゃもじゃです!
「現代の軍事戦略入門」
(エリノア・スローン著 奥山真司、関根大介訳)
本書は、軍事戦略理論を古典から現代までコンパクトにまとめており、軍事戦略の変遷を一般の読者でも理解できる入門書です。
なかなか知ることのできない、現代の戦略理論に重点が置かれている一方、基礎となった古典的理論にも、目配りされております。
本書より、前回のエアパワー1990年代に続き、2000年代のエアパワー理論を要約してご紹介します。
■概 略
・2000年代のエアパワー理論は主に、90年代のエアパワー理論の枠組み(戦略的効果、斬首、懲罰etc)をさらに議論を深化させたものと、新しいものとしてはアフガニスタン式の現地部隊+西側特殊部隊+エアパワーの統合的使用に関する議論がある。
■エアパワーの戦略的効果?
・セルビアに対してNATO軍が行なった78日間の爆撃「アライドフォース作戦」。この作戦では、エアパワーによる爆撃のみで、地上軍を派遣することなく勝利を得た史上初の作戦となった。一部の専門家は、ドゥーエが唱えた「エアパワー単独による勝利」に近づいたと考えた。
・しかし、その後の研究によると、エアパワーは確かにその時に使用された唯一の軍事力であったが、同時にNATOによる地上戦力投入の脅し、セルビアエリート層への経済・外交面での圧力、セルビアの国際政治的な孤立等が指摘されており、「エアパワー単独による勝利」をアライドフォース作戦が証明したことにはならない、と現在では認識されている。
■懲罰の有用性
・懲罰とは敵国の敵国の商業・工業的施設に対する爆撃。爆撃により物質的・精神的に打撃を与え、敵国の一般市民=非戦闘員を「懲罰するというもの。その結果、爆撃された市民の怒りが自国政府に対して起こり、政権が存続できずに、戦争が終結するというのがドゥーエの考え方。
・しかし、この考え方は、第二次大戦時のドイツによるロンドン空襲により、間違っていることが証明された。ロンドン市民の怒りはドイツに向けられたからである。
・冷戦後のアライドフォース作戦では、しかし、この懲罰が効いたように見え、専門家の中には、効果があると結論づけた者もいる。
・一方、湾岸戦争では、五週間にわたる爆撃でもイラクの精鋭部隊はまだ戦う意思をもっていた。空爆によって彼らの士気を叩くことはできなかったのである。
・このように懲罰の有用性については、まだ議論が続いている。
■継続的監視
・航空阻止とはエアパワーによる敵インフラの破壊や、地上・洋上の敵戦略の破壊を目的としたもの。
・航空阻止については、戦略的な効果があると認められている。
・しかし、ペンタゴンのデータを元にした分析によると、動かずに防御を重視する敵部隊を発見することは、砂漠という開けた環境の中でも難しく、ましてやセルビアのような山岳地帯ではさらに難しく、そのうえ囮と区別することは腹立たしいほどに困難だったという。
・その後、無人機の発展、多くの情報の一元化等により、かつてないほど明確な情勢認識を生み出せるようになった。
これらの進化は「継続的監視」という新しい概念の登場につながっている。
・アフガニスタン戦争では「継続的監視」がIED(道路上の即席爆発装置)への警戒から、さらに重視されるようになった。さらに継続的監視は、精密攻撃と合わさり「無人機による戦闘」という新しいエアパワーの概念につながり、CIAによっても用いられるようになった。
■斬 首
・斬首とは敵の重心(軍の司令部や政治的意思決定機関等)を精密攻撃によって、ピンポイントで破壊することを狙ったもの。
・専門家からは効果がないという警告があったにも関わらず、(一撃で敵を叩ける)その魅力から、サダム・フセインを狙った「衝撃と畏怖」作戦、タリバンのリーダーを狙った「不朽の自由」作戦が実施された。いずれも失敗。
・斬首攻撃は、正確かつタイミングの良い軍事的な諜報に多くを依存しており、また空爆が成功したとしても次の指導者がこちらが望む方向に政策転換するか予測することができないため、成功につながるとは言い切れない。
■新たな挑戦
・2000年代初期のアフガニスタン戦争、イラク戦争において、エアパワーと地上部隊との統合作戦は質的に新しい時代に入った。エアパワーのテクノロジーの進化により、エアパワーとランドパワーが同時に使われた場合は効果がさらに上がるようになった。
・新しい枠組みとして、現地の部隊(米軍ではない)とアメリカの特殊部隊、そして精密誘導兵器で武装したエアパワーとの組み合わせで、アフガニスタン式といわれる。アフガニスタンでは、米軍の特殊部隊と北部同盟+エアパワー、イラクでは、米軍特殊部隊とクルド人部隊+エアパワー、リビアではNATOが同じような方法をとった。
・専門家の間では、効果があるとするものと、主に現地部隊の能力(の欠如)による危険性を指摘するものとで意見が分かれている。

以上でエアパワー編は終了です。
次回すこし時間をあけてから「ゲリラ戦の理論」をお届けする予定です。
「現代の軍事戦略入門」
(エリノア・スローン著 奥山真司、関根大介訳)
本書は、軍事戦略理論を古典から現代までコンパクトにまとめており、軍事戦略の変遷を一般の読者でも理解できる入門書です。
なかなか知ることのできない、現代の戦略理論に重点が置かれている一方、基礎となった古典的理論にも、目配りされております。
本書より、前回のエアパワー1990年代に続き、2000年代のエアパワー理論を要約してご紹介します。
■概 略
・2000年代のエアパワー理論は主に、90年代のエアパワー理論の枠組み(戦略的効果、斬首、懲罰etc)をさらに議論を深化させたものと、新しいものとしてはアフガニスタン式の現地部隊+西側特殊部隊+エアパワーの統合的使用に関する議論がある。
■エアパワーの戦略的効果?
・セルビアに対してNATO軍が行なった78日間の爆撃「アライドフォース作戦」。この作戦では、エアパワーによる爆撃のみで、地上軍を派遣することなく勝利を得た史上初の作戦となった。一部の専門家は、ドゥーエが唱えた「エアパワー単独による勝利」に近づいたと考えた。
・しかし、その後の研究によると、エアパワーは確かにその時に使用された唯一の軍事力であったが、同時にNATOによる地上戦力投入の脅し、セルビアエリート層への経済・外交面での圧力、セルビアの国際政治的な孤立等が指摘されており、「エアパワー単独による勝利」をアライドフォース作戦が証明したことにはならない、と現在では認識されている。
■懲罰の有用性
・懲罰とは敵国の敵国の商業・工業的施設に対する爆撃。爆撃により物質的・精神的に打撃を与え、敵国の一般市民=非戦闘員を「懲罰するというもの。その結果、爆撃された市民の怒りが自国政府に対して起こり、政権が存続できずに、戦争が終結するというのがドゥーエの考え方。
・しかし、この考え方は、第二次大戦時のドイツによるロンドン空襲により、間違っていることが証明された。ロンドン市民の怒りはドイツに向けられたからである。
・冷戦後のアライドフォース作戦では、しかし、この懲罰が効いたように見え、専門家の中には、効果があると結論づけた者もいる。
・一方、湾岸戦争では、五週間にわたる爆撃でもイラクの精鋭部隊はまだ戦う意思をもっていた。空爆によって彼らの士気を叩くことはできなかったのである。
・このように懲罰の有用性については、まだ議論が続いている。
■継続的監視
・航空阻止とはエアパワーによる敵インフラの破壊や、地上・洋上の敵戦略の破壊を目的としたもの。
・航空阻止については、戦略的な効果があると認められている。
・しかし、ペンタゴンのデータを元にした分析によると、動かずに防御を重視する敵部隊を発見することは、砂漠という開けた環境の中でも難しく、ましてやセルビアのような山岳地帯ではさらに難しく、そのうえ囮と区別することは腹立たしいほどに困難だったという。
・その後、無人機の発展、多くの情報の一元化等により、かつてないほど明確な情勢認識を生み出せるようになった。
これらの進化は「継続的監視」という新しい概念の登場につながっている。
・アフガニスタン戦争では「継続的監視」がIED(道路上の即席爆発装置)への警戒から、さらに重視されるようになった。さらに継続的監視は、精密攻撃と合わさり「無人機による戦闘」という新しいエアパワーの概念につながり、CIAによっても用いられるようになった。
■斬 首
・斬首とは敵の重心(軍の司令部や政治的意思決定機関等)を精密攻撃によって、ピンポイントで破壊することを狙ったもの。
・専門家からは効果がないという警告があったにも関わらず、(一撃で敵を叩ける)その魅力から、サダム・フセインを狙った「衝撃と畏怖」作戦、タリバンのリーダーを狙った「不朽の自由」作戦が実施された。いずれも失敗。
・斬首攻撃は、正確かつタイミングの良い軍事的な諜報に多くを依存しており、また空爆が成功したとしても次の指導者がこちらが望む方向に政策転換するか予測することができないため、成功につながるとは言い切れない。
■新たな挑戦
・2000年代初期のアフガニスタン戦争、イラク戦争において、エアパワーと地上部隊との統合作戦は質的に新しい時代に入った。エアパワーのテクノロジーの進化により、エアパワーとランドパワーが同時に使われた場合は効果がさらに上がるようになった。
・新しい枠組みとして、現地の部隊(米軍ではない)とアメリカの特殊部隊、そして精密誘導兵器で武装したエアパワーとの組み合わせで、アフガニスタン式といわれる。アフガニスタンでは、米軍の特殊部隊と北部同盟+エアパワー、イラクでは、米軍特殊部隊とクルド人部隊+エアパワー、リビアではNATOが同じような方法をとった。
・専門家の間では、効果があるとするものと、主に現地部隊の能力(の欠如)による危険性を指摘するものとで意見が分かれている。

以上でエアパワー編は終了です。
次回すこし時間をあけてから「ゲリラ戦の理論」をお届けする予定です。











